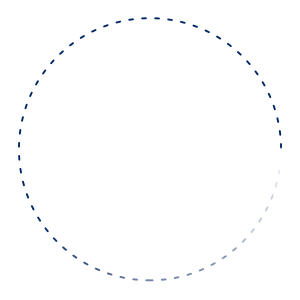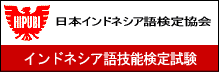インドネシア語講座
インドネシア語会話を定期的にスキット別にご紹介していきます。
- Vol.25 「所要時間をたずねる」(DINA)
- Vol.24 「荷物をトランクに入れる」(NINO)
- Vol.23 「行先を告げる」(MAYUMI)
- Vol.22 「タクシーチケットを購入する」(KEIKO)
- Vol.21 「タクシー乗り場をさがす」(CHIKO)
- Vol.20 「両替所2 小銭にしてもらう」(KEIKO)
- Vol.19 「両替所で 」(近藤/アルビー)
- Vol.18 「税関審査 」(CHIKO)
- Vol.17 「預けた荷物を受け取る 」(小林)
- Vol.16 「入国審査 」(近藤)
- Vol.15 「別れのあいさつ」(KEIKO)
- Vol.14 「しばらくぶりのあいさつ」(アルビー)
- Vol.13 「あいづちをうつ」(CHIKO)
- Vol.12 「聞き返す」(小林)
- Vol.11 「上手に断る」(近藤)
監修者
Dominicus Bataone(ドミニクス バタオネ) |
1931年インドネシア、フローレス、ルンバタ島ラマレラ村生まれ。故郷の村の男たちは今もなお手漕ぎの舟と手作りの銛による伝統的な鯨漁を行い、女たちは男たちが捕った鯨の肉を山の民と物々交換している。中学校からジャワ島で教育を受け、国立パジャジャラン大学大学院文学部修了。現在、INJカルチャーセンター、インドネシア語主任講師。都会育ちだが、他のインドネシア人同様、自分の出身地をこよなく愛す。著書(共著)は「ちょばちょばインドネシア語1」、「ちょばちょばインドネシア語2」INJ出版、「バタオネのインドネシア語初級」、「バタオネのインドネシア語中級口語編」、「インドネシア語で手紙を書く」めこん、「CD付インドネシア語が面白いほど身につく本」中経出版ほか多数。 |
講師
近藤 由美(こんどう ゆみ)最初に訪れたインドネシアはイリアン・ジャヤ(現在はパプア)。空港に降り立った途端、腰ミノなど独特な民族衣装に身を包んだ人々の出迎えを受けて驚くが、彼らの優しさに触れて数年後に再訪。その後、インドネシアの他の島々を回るうちに、地域によって人種、言語、宗教、生活習慣が全く違うインドネシアの奥深さを知る。現在、INJカルチャーセンター代表。インドネシア語、バリ語、バリ舞踊、ガムラン、バティックなどの講座を通じて、インドネシアの言葉や文化を紹介している。著書は「写真対応インドネシアを旅する会話」三修社、「ちょばちょばインドネシア語1」 INJ出版(共著)、「CD付インドネシア語が面白いほど身につく本」中経出版(共著)、「ニューエクスプレス マレー語」白水社(共著)、「タビトモ会話マレーシア マレー語」(JTBパブリッシング)ほか多数。 |
|
小林 和夫(こばやし かずお)1966年東京生まれ。創価大学文学部社会学科在学中にインドネシア大学に派遣留学。留学時に搭乗したガルーダ・インドネシア航空の成田発ジャカルタ行きは、国内・海外を含めて初めての飛行機搭乗だった。民間企業を経て、東京都立大学大学院都市科学研究科博士課程単位取得退学。博士(都市科学)。専攻はインドネシア地域研究。現在、創価大学准教授。歌手イワン・ファルスのファナティックなファン。著書に『ちょばちょばインドネシア語2』INJ出版(共著)、主要論文に「ゴトン・ロヨンが制度化されるとき」(『東南アジア―歴史と文化』33 号)、「インドネシアにおける『伝統』の実践とポリティクス」(『社会学評論』55-2号)がある。 |
|
橋本 章子(はしもと あきこ)
|
通称、CHIKO。 1971年生まれ。スラバヤに駐在していたインドネシア好きの父親の影響で、幼少の頃からインドネシアの調度品に囲まれ、おやつはクルプック、ピアノの発表会にはスンバ織のドレスという環境で育つ。15歳でインドネシアへ単身留学し、インターナショナルスクールを経てジャカルタの現地の高校へ。スラバヤ2 年、ジャカルタ5年、シンガポールに7年…と人生の約半分を東南アジアで生活する。現在、INJカルチャーセンター講師として、総合講座のほかに会話も担当。「文法風のカタイ会話」ではなく、市販のテキストにはない「実際にネイティブが話す自然な会話」の授業にファンも多い。テレビ局のビデオ翻訳や政府要人、研修生の通訳でも活躍。著書(共著)は、「ことたびインドネシア語」白水社。
|
佐藤 辰彦(さとう たつひこ) |
通称、Bapak佐藤。1940年東京生まれ。大学卒業後、貿易会社に入社。東南アジア向けの輸出業務担当になり、出張でジャカルタ、スラバヤを訪問。出張前は、汚くて危ない国だと周囲からさんざん脅かされたが、のどかな風景を目にし、親切でのんびりした現地の人たちと接するうちに、すっかりインドネシアが気に入る。やがて、英語での表面的な付き合いに物足りなさを感じ、インドネシア語を学ぼうと決心。神田外語学院でインドネシア語を学んだ後、INJカルチャーセンターのインドネシア語講座に通う。その後、多くの人にインドネシアの魅力を伝えたいと思うようになり、自らもインドネシア語講座を担当。社会、地理、歴史などインドネシア全般に関する知識を広めながら、インドネシア語を習得することを目指す。
|
宮岡 敬子(みやおか けいこ) |
通称、KEIKO。大学卒業後、商社勤務を経てインドネシア大学文学部(現文化学部)外国人向けインドネシア語プログラム(BIPA)にてインドネシア語を学ぶ。外国語へのコンプレックスに悩まされながらも、現地の言葉が話せることで現地での生活が全く違ったものへと変化することを身を持って体験。同大学ジャワ語学科ジャワガムラン部に唯一の外国人として所属し数々の演奏会に参加。同大学講師 及び学生への日本語講義(ボランティア)を通じてインドネシア人との交流に努める。現在、INJカルチャーセンター・インドネシア語講師。自らが参加するアマチュアロックバンドでインドネシアのロック、ポップスも演奏する変り種。著書(共著)は「イラスト会話ブックバリ島インドネシア語」JTBパブリッシング。
|
Dina Faoziah(ディナ フォアジア) |
1977年生まれ。ガジャ・マダ大学経済学部卒業後、JICAのプロジェクトにかかわった後、国費留学生として来日。東京外国語大学大学院地域文化研究科博士前期課程を修了し、現在、東京農工大学大学院連合農学研究科博士課程在学中。2004~2006年にNHKラジオ日本・インドネシア語班アナウンサーとして在籍。現在、INJカルチャーセンター・インドネシア語講師としてインドネシア語入門~上級講座を担当し、翻訳家・ナレーターとしても活躍中。共同翻訳書は『Titipan Kilat Penyihir (邦題:魔女の宅急便)』(PTGramedia PustakaUtama)。『イラスト会話ブックバリ島インドネシア語』JTBパブリッシングの「日本の紹介」欄翻訳担当。
|
湧口 真由美(ゆぐち まゆみ) |
通称、MAYUMI。1973年生まれ。大学在学中にバリ島を一人旅し、バリの魅力にとりつかれる。大学、大学院修士課程で文化人類学を専攻し、バリの文化とりわけバリ人画家の研究に取り組む。大学院修了後もインドネシアへの興味が尽きず、公務員の職を辞してインドネシア大学文化学部外国人向けインドネシア語プログラム(BIPA)に語学留学する。留学中はインドネシア人学生たちと寝食を共にする濃密な下宿生活を送り、長距離バスや国営フェリーでインドネシアの各地を旅し、インドネシアの生活習慣やさまざまな地域の文化を身をもって体験する。現在はINJカルチャーセンター講師としてインドネシア語講座を担当。著書(共著)は「イラスト会話ブックバリ島インドネシア語」JTBパブリッシング。
|
Rosnaeni Tawang(ロスナエニ タワン) |
通称、ニノ。1971年インドネシア南スラウェシ島マカッサル生まれ。ハサヌディン大学農学部卒業後、農業・環境調査の業務に携わる。2000年に留学の ため来日。日本語を学ぶために沖縄で国際文化学科に入り、留学生や沖縄県民と交流しながら、小・中・高等学校でインドネシア文化や言葉を紹介する。毎年、 名護市で開催される国際料理フェアーに参加してインドネシア料理を披露したり、沖縄の伝統舞踊エイサーを学び、同級生と一緒にブラジルでエイサーを踊るな ど、国際交流に強い関心がある。2005年より早稲田大学アジア太平洋研究科で国際関係を研究中。現在、INJカルチャーセンター・インドネシア語講師。 言葉だけでなく、文化や習慣、コミュニケーションの楽しさを重視して教えている。 |
![]() 掲載のインドネシア語に関するお問い合わせは、INJカルチャーセンターにお願いします。
掲載のインドネシア語に関するお問い合わせは、INJカルチャーセンターにお願いします。
INJカルチャーセンターはこちら